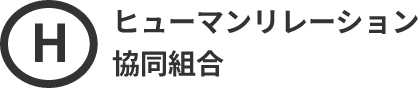よくあるご質問
Frequently Asked Question
監理団体はどのように選ぶといいですか?
監理団体を選ぶ際は、以下のチェックリストに基づいてご検討ください。
専門知識・経験
- 技能実習制度に関する専門知識と経験は十分か。
- 過去の実習生の満足度は十分か。
サポート力
- 実習生からの相談に迅速かつ適切に対応できているか。
- 通訳や母国語スタッフの在籍状況はどうか。
- 緊急時の対応体制が整っているか。
- 私生活に関わるサポート体制はあるか。
- 母国語でも相談窓口はあるか。
実習生への教育
- 入国後の、日本語等の教育プログラムが整っているか。
- 生活ルールや日本語能力向上のサポートが充実しているか。
- 企業が求める教育実施時の対応力。
監理費
- 提供されるサービスに見合った監理費が設定されているか。
(安価すぎる場合は、サービスの質や支援の充実度に問題がある可能性もあります。)
受入れ前、最初に何をしたらいいですか?
業種や規模に応じて、受け入れ可能な条件が異なります。
実習生の受け入れを検討している仕事内容や、貴社の従業員数などをお知らせください。
そのほか、ご不明点やご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
実習生の受け入れに関する具体的な条件や手続きについても、ご説明させていただきます。
外国人技能実習生はどのように選ばれますか?
受入れ企業様に、現地またはオンライン面接をご実施いただきます。
知能テスト、算数テスト、F-RATテスト等や、体力測定、健康診断をクリアした候補者の中から更に高い倍率で選考が行われます。
受入れ企業様が直接、又はリモートで技能実習生候補者の面接を行い、性格や経験等を確認していただくことで、適切な選考結果が得られます。
出稼ぎ志向ではなく、日本の技能実習制度をしっかりと理解している応募者を選考することが重要です。
文化や習慣の違いはありますか?
文化や習慣の違いはもちろんあります。
日本国内での職場及び生活のいろいろな場面で問題が生じないように、入国前・入国後講習の中で日本の文化や習慣、各ルール及び日本人の考え方を理解して頂くための講習を行います。
日本語に問題はありませんか?
技能実習生には入国前と入国後に日本語の教育が義務づけられているため、簡単な日本語なら理解し、話すことができます。
実習生の講習とはどういったものですか?
大きく分けて「日本語力の向上」と「日本における生活慣習への理解」「日本の法的知識」の3つが講習の軸となります。
日本語力の向上
基本的な日本語を理解する事が出来る「日本語能力試験4級」を目標としています。
「読む・書く」は勿論の事、「聞く・話す」という、コミュニケーション能力に重点を置いた講習も行います。
日本における生活習慣への理解
職場での仕事への取組み姿勢は勿論の事、私生活で周りの住民の皆様と円滑な生活が行える様に、日本の生活ルール、習慣、マナー等の指導もしっかりと行います。
日本の法的知識
働く上で必要な「労働法」をはじめ、生活に関わる法律、交通ルール等の指導を行います。
会社内における各種規定及び業務上必要な知識、安全管理に必要な知識に関しても、適宜ヒューマンリレーション協同組合の担当が企業様と連携し指導・教育を行いますのでご安心下さい。
配属後の日本語のフォローはどうなっていますか?
実習生は企業配属後、研修で習った日本語と専門用語を含む現場での日本語の違いに戸惑うことが少なくありません。
ヒューマンリレーション協同組合は配属後も日本語学習へのフォローを行っております。
また、年に1回必ず日本語能力試験の受験を義務付け、合格者に対し褒賞金制度を設け、継続的な日本語力向上への取組を行っております。
実習生の病気や怪我などのトラブル対応はどうしたら良いですか?
実習実施企業様ごとに専任の担当者がおります。
実習生の病気や怪我などが発生した場合など、お困りの際は直接各担当にご連絡下さい。
また、実習生が母国語で直接相談できる体制も整えておりますのでご安心ください。
なお、実習生は雇用関係の下に置かれるため、一般の労働者と同じく労働保険や社会保険(健康保険など)の対象となります。
健康保険診療の場合には必ず自己負担費用がかかるため、公的保険でカバーされない費用を補完する技能実習生総合保険などへの一括加入を行っております。
実習生の失踪対策はしていますか?
ヒューマンリレーション協同組合では過去に一度も失踪者を出しておりません。
採用時から、実習実施企業様に関わる情報を明確に伝え雇用に至っておりますので、入国後のミスマッチが生じていないことが、失踪者が出ない大きな要因であると考えます。
また、入国後もヒューマンリレーション協同組合の各担当者が実習生と密なコミュニケーションを取り、問題のある方との接触及び違法行為に巻き込まれないための注意喚起・教育を行っている事が良き結果に繋がっていると考えます。